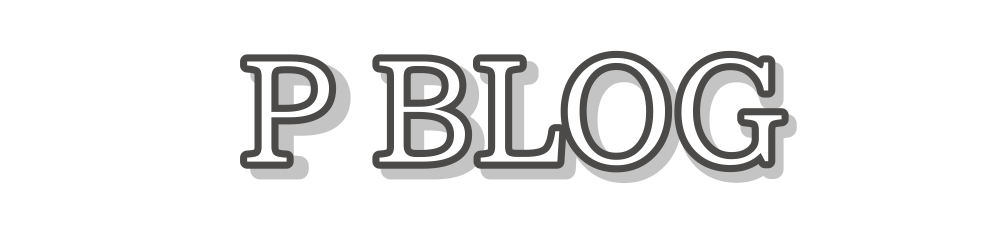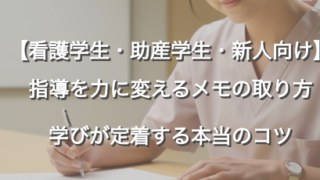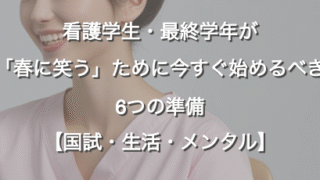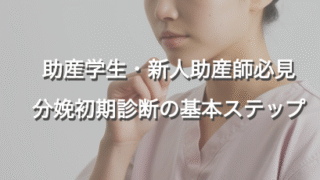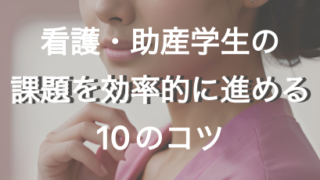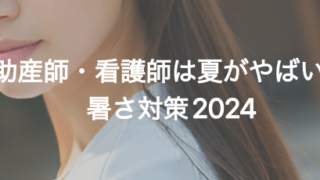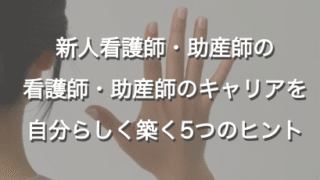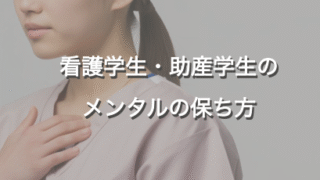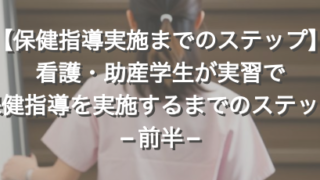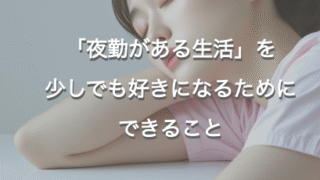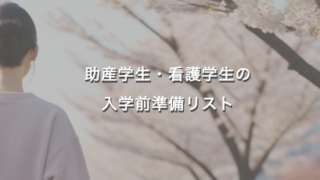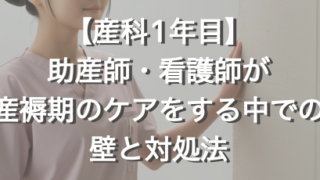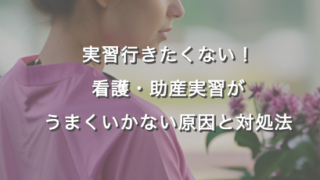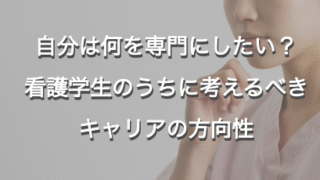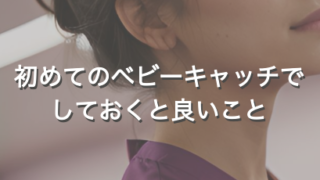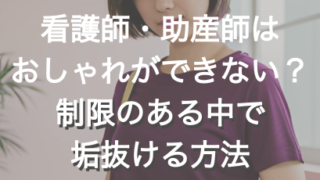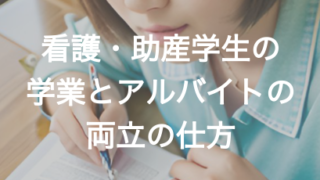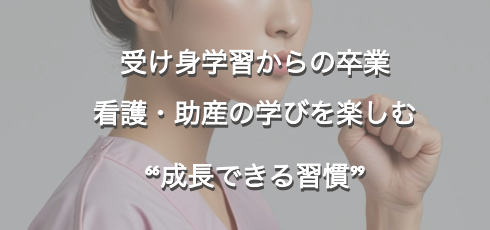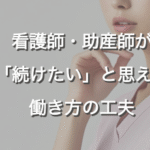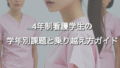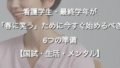[PR]記事内のアフィリエイトリンクから収入を得る場合があります
こんにちは、Pです✨
看護や助産の学びは、知識も技術も求められるからこそ大変です。

でもその一方で、同じ環境でも“伸びる人”と“伸び悩む人”がいます。
その差は、能力ではなく 「学び方」
特に、受け身の学びから抜け出せるかどうかは、成長スピードを大きく左右します☝️
この記事では、看護学生・助産学生、そして臨床に出て間もない看護師・助産師が、
学びを楽しみながら成長できる習慣をつくる方法をわかりやすくまとめました🍀
今日からできる小さな行動で、学びは大きく変わります💪
受け身学習からの卒業|看護・助産の学びを楽しむ“成長できる習慣”

⇓
なぜ受け身学習では成長が止まるのか

受け身学習の特徴とデメリット
受け身学習とは、「言われたことをやる」「与えられた情報だけで学ぶ」状態のこと。
これは一見ラクに見えますが…
- 自分の理解不足に気づきにくい
- 知識が表面的で応用が難しい
- 実習で“何を見ればいいか”がわからない
- 学びが受動的で疲れやすい
といったデメリットがあり、成長が頭打ちになりやすいのが特徴です。
“教えてもらえる前提”が成長を妨げる理由

医療現場は常に忙しく、指導する時間も限られています。
「丁寧に教えてもらえるのが当たり前」ではありません。
「どうしたら学べるか?」と自分で動くことで、学びの量と質は確実に上がっていきます。
看護・助産の学びを楽しむために必要な視点
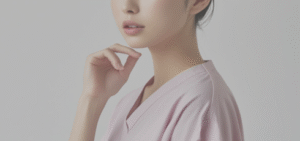
学びを「受け取る姿勢」を整える
主体的な学びの出発点は、“自分が何を理解していて、何がわかっていないのか” を整理すること。
これができると授業も実習も情報が入りやすく、
必要な学びを自分で取りに行けるようになります。
学びのありがたさに気づくと行動が変わる
実習での経験、授業内容、先輩からのアドバイス。
これらはすべて「当たり前」ではありません。
“学ばせてもらっている環境”という視点があるだけで、
行動の質は自然と変わっていきます。
受け身から抜け出す“成長できる習慣”

1|資料の整理習慣(情報の受け取り方が変わる)
配布資料・授業ノート・実習のメモ。
これらを「探せない状態」のままにしていませんか?
整理されているだけで…
- 必要な情報がすぐ見つかる
- 頭の中も整い、理解が深まりやすい
- 復習がスムーズで定着しやすい
と、学びの入り口が大きく変わります。
2|課題を丁寧にこなす(理解の深さを育てる)
課題は、成長ポイントが凝縮された“学びのヒント集”です。
ただ提出のためにこなすのではなく、
「なぜこの課題が出ているのか?」
を考えるだけで理解度が一気に変わります。
3|振り返り習慣をつくる(成長の軌道が見える)
1日5分でいいので、
を書き留めてみる。小さなメモで十分です。
“振り返り”は、自分の成長を見える化してくれます。
4|質問の仕方を変える(主体性が育つ)
「わかりません」では、情報が得られません。
「ここまで調べたのですが、ここが理解できません」
と伝えることで、相手のアドバイスは何倍も深くなります。
質問の質が変わると、学びの質も一気に変わります。
5|学びを“現場で使うために整理する”(理解が確かな記憶になる)
学んだことは、ただ覚えるだけでは定着しません。
“使うために整理する” ことで、初めて自分の知識になります。
具体的には、
- 授業内容を自分の言葉でノートにまとめ直す
- 実習で見たことと授業の知識を結びつける
- 似た症状やケアの違いを比較してまとめる
- 明日の実習で使える形に1ページに整理する
こうした整理こそ、実習や演習でそのまま使えるアウトプットです。
アウトプットとはSNSでの発信ではなく、
現場で使える形に変換することが、もっとも強い学び方です。
6|学びを楽しむ“余白”をつくる(セルフケアが学びを支える)
疲れたまま学ぼうとしても、頭に入りません。
コーヒーを飲む、深呼吸をする、好きな香りを使う。
心の余白があるだけで、学びへの向き合い方は穏やかになり、吸収力も高まります。
主体的な学びはキャリアを守る

早いうちに学び方を身につけた人が後で楽になる
主体的に学ぶ力は、社会人になってからもあなたを助けます。
環境が変わっても、学び続けられる“土台”になるからです。
看護・助産の未来を支える“学び続ける姿勢”
医療は常に進化しているからこそ、学び続ける姿勢はあなた自身を守り
患者さんの安心にもつながります。
まとめ|今日からできる小さな一歩

受け身学習を手放すことは、特別なことではありません。
小さな積み重ねが未来のあなたをつくります。
「看護・助産の学びを、もっと楽しめる自分へ。」
P BLOGがお役に立ちますように✨
\ ポチッとランキング応援お願いします! /