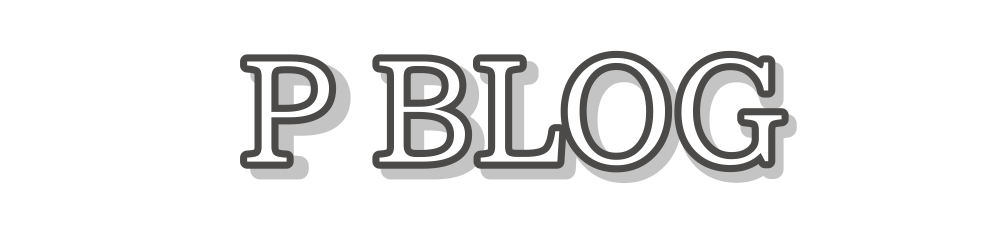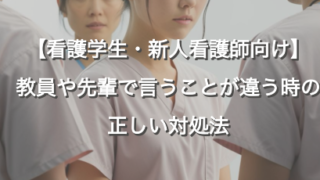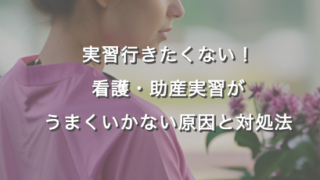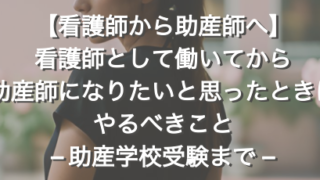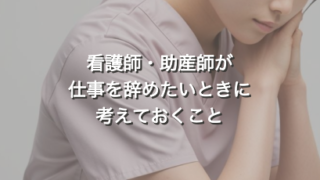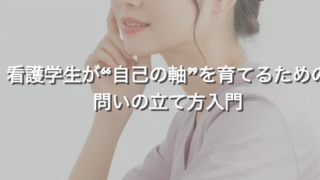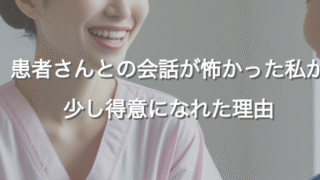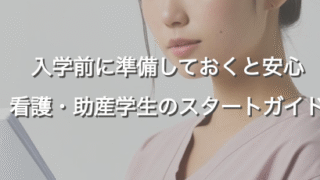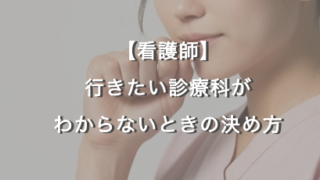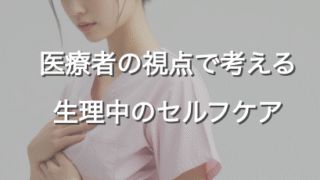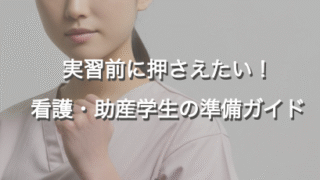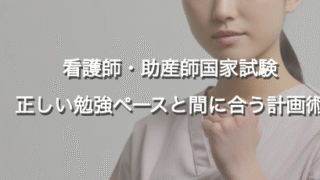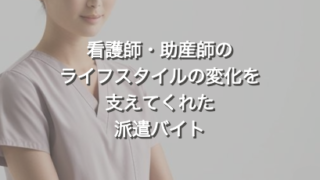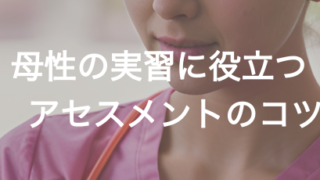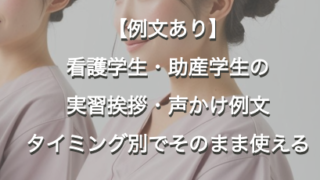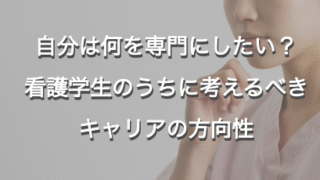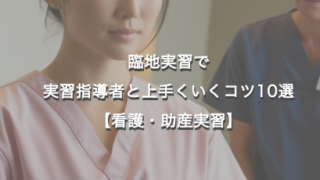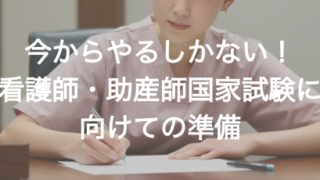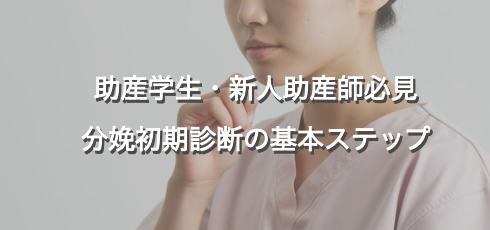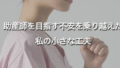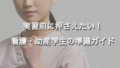[PR]記事内のアフィリエイトリンクから収入を得る場合があります。
こんにちは、Pです✨
助産学生や新人助産師にとって、
初めて「分娩を担当する」ときの緊張感は特別なものです。

と不安になることも多いでしょう。
参考書や講義で学んだ知識は大切ですが、実際の現場ではそれだけでは不十分な場面もあります。
この記事では、分娩を担当するときに押さえておきたい観察項目・アセスメントの流れ・情報共有のコツをステップ形式で解説します。
新人助産師や助産学生の皆さんが
「実習や勤務で役立つ!」
と思えるような実践的な内容をお届けします🍀
助産学生・新人助産師必見|分娩初期診断の基本ステップ

⇓
分娩の初期診断とは?基本を押さえよう

分娩初期診断の目的
分娩初期診断とは、妊産婦の入院時、分娩開始時、受け持ち時などに
母体と胎児の状態を把握し、安全に分娩を進めるための第一歩です。
目的は以下の通りです。
- 母体の全身状態と既往歴の把握
- 分娩の進行度合いを評価
- 胎児の健康状態を確認
- 今後のケア・分娩方針の見通しを立てる
助産学生・新人助産師が悩みやすい点
- どこまで観察し情報収集するべきか
- 医師や先輩助産師にどう報告するか
- 限られた時間で何を優先するか
分娩初期診断の基本ステップ

①母体の観察
\ 例 /
- バイタルサイン(体温・血圧・脈拍・呼吸数)
- 感染症や既往歴の有無
- 妊娠経過や特記事項の確認
- 入院時の全身状態の観察
②分娩経過の確認
\ 例 /
- 陣痛の有無・間隔・強さ
- 破水の有無や羊水の性状
- 出血の有無と量
- 子宮口の開大度や展退度
③胎児の評価
\ 例 /
- 胎児心拍数の確認(NSTや聴診器)
- 胎位・胎向の把握
- 推定体重の確認
- 羊水混濁の有無
④情報共有と記録
\ 例 /
- 観察結果を簡潔にまとめる
- 担当医師やスタッフに報告
- チームでの情報共有を徹底する
よくあるつまずきポイントと対策

観察に時間がかかってしまう
\ 対策 /
優先順位をつけて「母体・胎児の安全に直結する項目」から確認する。
報告がうまくできない
\ 対策 /
SOAP形式で整理して伝える。
「母体」「胎児」「分娩経過」の3つにまとめるとスムーズ。
情報を見落としてしまう
\ 対策 /
チェックリストを活用して抜け漏れを防ぐのが効果的。

実践で役立つチェックリスト活用法

分娩初期診断は、限られた時間で多くの情報を収集しなければなりません。
そこで役立つのが ポケットサイズで使えるチェックリスト です。
- 観察項目や確認事項を一覧化
- プリントアウトして切れば、ポケットノートにそのまま貼れる仕様
- 実習や勤務中でもサッと見返せて安心
👉 私自身が「これがあれば安心」と感じた内容をまとめ、
noteにまとめました。
実習や新人時代に役立つ実践的な工夫を詰め込んでいます。
まとめ|不安を力に変えて、初めての分娩に臨もう
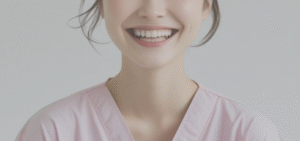
助産学生や新人助産師にとって、分娩初期診断は最初の大きなハードルです。
ですが、観察の流れや優先順位を押さえ、実践で役立つチェックリストを取り入れることで
自信を持って臨めるようになります。
👉 初めての分娩介助に備えて、
ポケットサイズで使える「分娩初期診断チェックリスト」
よかったらぜひ活用してください✨
\ ポチッとランキング応援お願いします! /