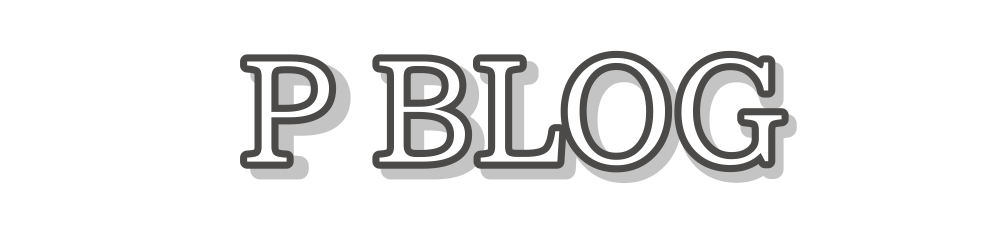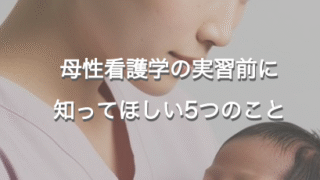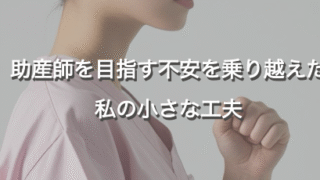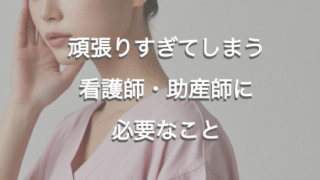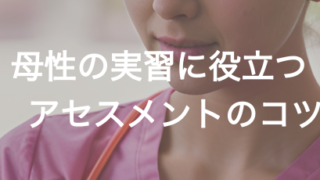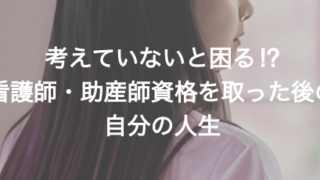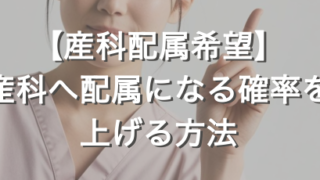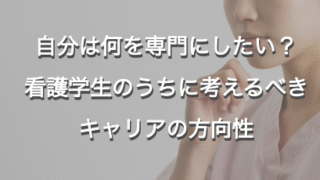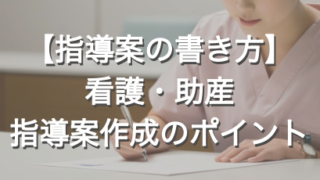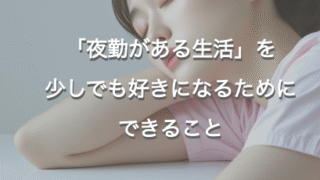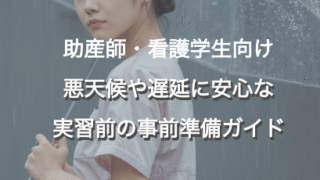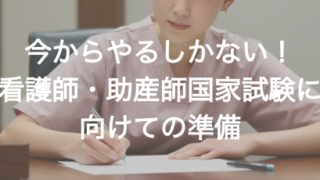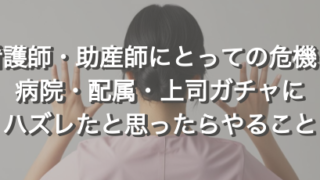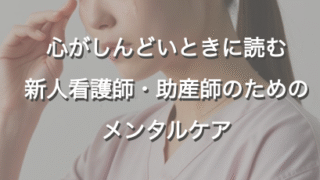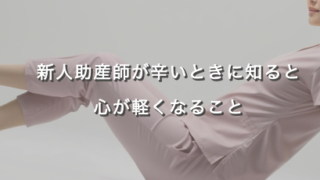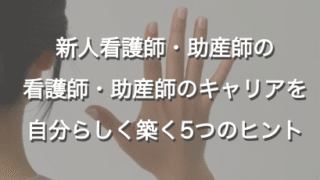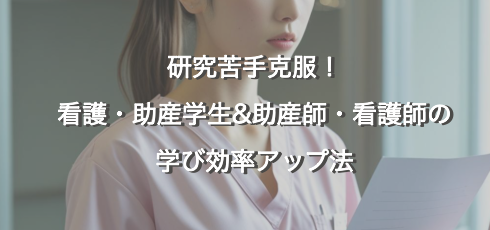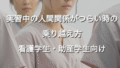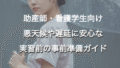[PR]記事内のアフィリエイトリンクから収入を得る場合があります。
こんにちは、Pです✨
看護学生・助産学生、そして看護師・助産師の皆さん、

研究やレポートって難しそう…

やり方がわからなくて手が止まる…
そんな経験はありませんか?
Pも昔は同じでした。
でも、大学や大学院での経験や臨床での経験を通して気づいたんです。
研究は怖いものじゃなく、学びや仕事をスムーズにするツールになる!
今回は、研究が苦手でも効率よく進められる方法を
学生も現役看護師・助産師も実践できる形で紹介します。
この記事を読めば、研究のハードルがグッと下がり
学業や仕事もスムーズに進みます。
研究苦手克服!看護・助産学生&助産師・看護師の学び効率アップ法

⇓
研究の始め方〜疑問の見つけ方

日常や実習から疑問を見つける
- 実践や観察で「なぜこうなるのか」を探す
- 教育制度や患者対応で気づいたことをメモ
- ケア効果や体制への疑問もテーマになる
実習や日常の業務の中で感じたことから探していくパターン🔍
社会的背景から疑問を広げる
- 家族・社会・経済的要因から課題を探す
- ガイドラインやWHOの指針とのギャップを確認
社会的背景は変化も早いため、意識して情報をキャッチしたり確認していく必要があります。
興味や関心から疑問を見つける
- 過去の実習や学業で気になった分野
- 技術・体制・統合医療・代替療法など
興味のあるテーマを選ぶと、研究が楽しく続けやすくなります。
先行研究&文献の確認
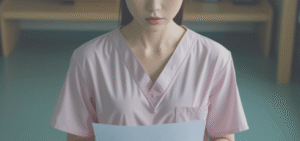
関心テーマのキーワード整理
- 例:「助産師」「マッサージ」「効果」など
- 複数のキーワードを組み合わせて検索
この過程がとっても大変ですが、大切なので頑張りましょう💦
文献検索と整理
- 医中誌などのツールで検索
- 概要を確認、必要なら全文確認
- 著者・テーマ・学会誌・年度を整理しておく
文献整理は「考察」や「はじめに」を書くときに役立ちます。
クリティークで論文理解を深める

- 文献全体の流れをチェック(背景・方法・結果・考察)
- 方法や結果が妥当か、分析手法は適切か
- 倫理的配慮や表記ルールも確認
クリティークを通して、自分の研究の方向性が明確になります。
研究計画から実施までの流れ

- テーマと研究目的を明確化
- 概念枠組みを整理
- 対象者選定
- データ収集方法決定(量的・質的研究)
- 調査実施
- 結果の集計・分析
- 考察
- 結論と今後の課題
手順は多いですが、一つずつ進めれば必ず完成します。
まとめ|研究の具体的な進め方を知って学習も仕事もスムーズに

研究をスムーズに進めるには、計画書の書き方や実施ステップをまとめておくのが効率的です。
P note「看護・助産の研究|研究嫌いだったPが乗り越えられた研究の進め方✏︎」では、
- 「研究って何から始めればいいの?」
- 「効率的に文献を整理する方法は?」
- 「クリティークの進め方がわからない」
といった悩みを解決できます。
学習や臨床の効率を上げたい方は、ぜひチェックしてみてください✨
\ ポチッと応援お願いします! /