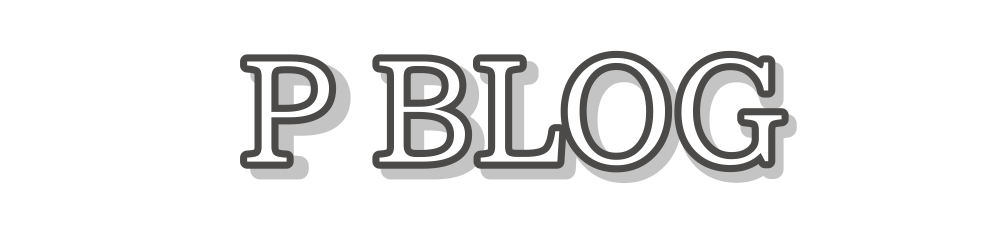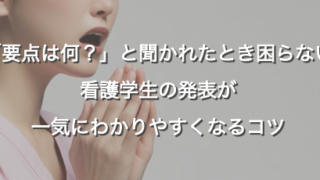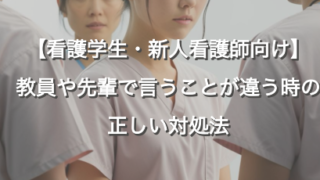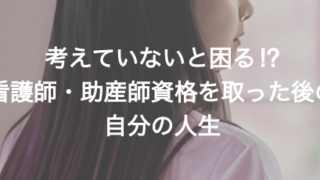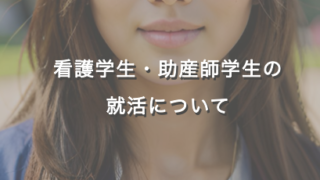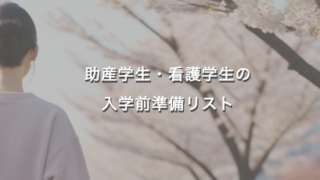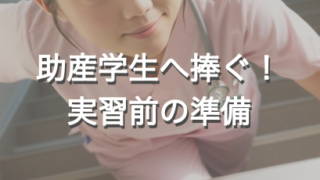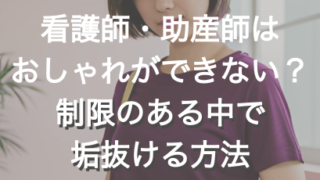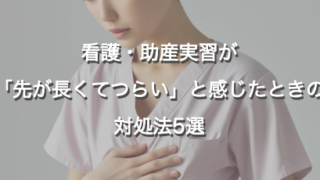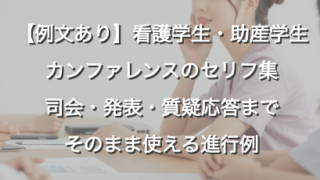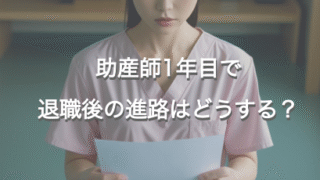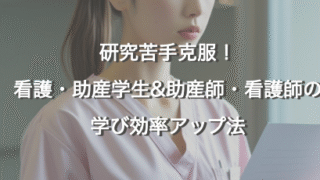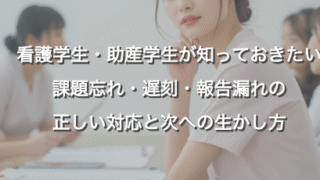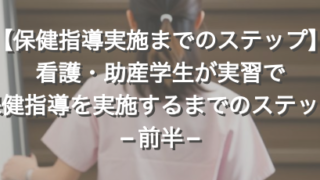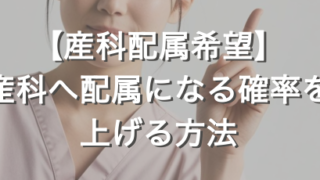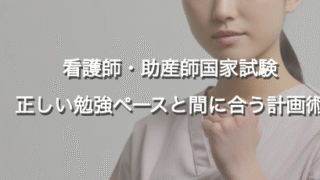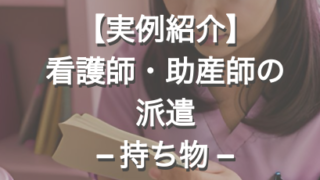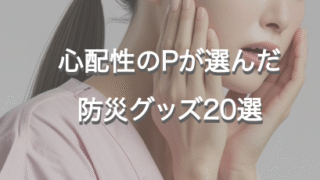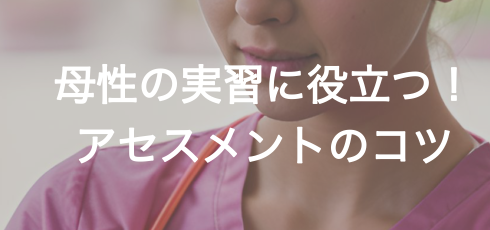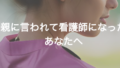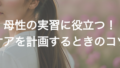[PR]記事内のアフィリエイトリンクから収入を得る場合があります
こんにちは、Pです。
今回はアセスメントのコツについてお伝えしたいと思います。
主に産科(母性)におけるアセスメントの考え方です。
アセスメントの仕方は学校や施設、先生によって異なります。
主軸は自分の環境に合わせて(学校の授業など)考えていただき
参考のひとつとしてみていただけると幸いです。
それではいってみましょう!
母性の実習に役立つ!アセスメントのコツ

⇓
アセスメントのコツ

アセスメントで問題点を明確にしていく
- 現状を丁寧に評価していく
- 生理的範囲を逸脱しているもの、逸脱しそうなもの(リスク)をピックアップ
- 生理的範囲を逸脱している、逸脱するリスクの要因を考える
- 【3】を個別性に当てはめて考えてみる
- 対象がより良い状態になるために、どのようにしたら良いか、どのような介入が必要か考える
- 【5】を個別性に当てはめて考えてみる
順番に見ていきましょう。
1.現状を丁寧に評価していく
まずは現状をひとつひとつ確認していきましょう。
母体・胎児・新生児の身体・精神・社会的側面などさまざまな角度から見ていきます。

今どのような状態なのか確認するには、正常値や生理的な変化(機序)を知っている必要があります。
また、起こりうるリスク(異常)についても学習しておきましょう。
2.生理的範囲を逸脱しているもの、逸脱しそうなもの(リスク)をピックアップ
ひとつずつ【1】を確認していくと
生理的範囲を逸脱しているもの、逸脱しそうなもの(リスク)が見えてきます。
これらを明確にしていきましょう。
3.生理的範囲を逸脱している、又は逸脱するリスクの要因を考える
【2】で出てきたものの、要因を考えていきます。
これは、その現象が起こる機序であったり、対象の特徴や治療や薬の影響などさまざまな要因があります。
これらの要因を全て考えたのちに、アセスメントの対象がどの要因に影響を大きく受けているのか考えていきましょう。

4.【3】を個別性に当てはめて考えてみる
【3】について、個別性(対象の特徴)に当てはめて考えてみます。
【3】の要因を背景(性格、身体的特徴、行動パターン、合併症、社会的背景など)と結びつけるように考えていくと繋がりが考えやすいです。
5.対象がより良い状態になるために、どのようにしたら良いか、どのような介入が必要か考える
まずは、一般的な具体策から考えていきます。
一般的な介入がわからない場合は、参考書など見るとイメージしやすいです。
6.【5】を個別性に当てはめて考えてみる
【4】をしっかりと考えられていると、具体策が出やすいです。
また、それを生活レベル(自立している方の場合、生活の中に組み入れて実習できるような方法)まで落とし込む作業が必要です。

【1】〜【6】のステップに加えていくこと

【1】〜【6】の各ステップに加えていくことがあります。
母性においては、アセスメントの対象が複数(主に妊婦・産婦・褥婦と胎児・新生児)になります。
そのため、双方のアセスメントをしていく中でそれぞれの関連性を常に意識していく必要があります。
機序や生理的な仕組みを理解すると、言わずもがな関連していることではありますが、初めは意識しないと切り離して考えがちです。
必ず関連性を理解しながらアセスメントを進めましょう。
さいごに

いかがでしたでしょうか。
アセスメントは、慣れていないときは何かを目安にしていかないとぼんやりとしたものになりがちです。
そのようなとき、参考のひとつとしてお役に立てると幸いです。
実習の中でもより大変なアセスメメント。
逆にできてしまえば、他のケアやコミュニケーションも円滑になるであろうアセスメント。
一緒に頑張っていきましょう!
※アフィリエイト広告を使用しています